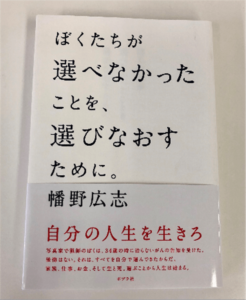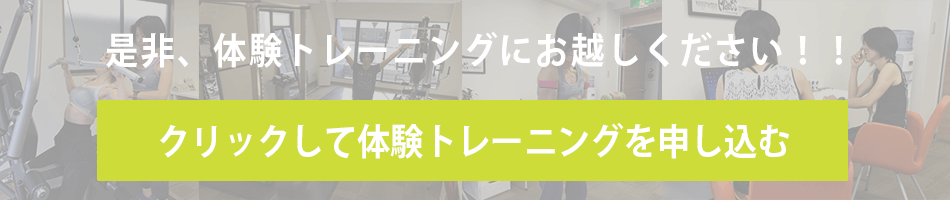本屋さんの平積みを眺めて回るのが好きです。
先日も特に探している本もなく
ぷらぷら平積みパトロールしてて
この題名に目が止まり、
その後も店内を一回りしたけど結局戻って中も見ず購入しました。
この本は、余命3年と宣告されたカメラマンの著書と奥さんと息子さんのことが軸となっています。
多発性骨髄腫
「治らないがん」と呼ばれていることも病名もこの本で初めて知りました。
このがんの特徴として、家族にトラウマを与えてしまうほど壮絶な最期を迎えてしまう、ということも。
自分の身に置き換えたら…想像を絶する恐怖でしかないです。
ただこの本はそこから闘病生活が描かれるのではなく
苦しい治療の後、歩けるようになった著者が、自身のブログ等に多数寄せられたメッセージの中から、どうしても会いたい人に会いに行く旅(取材内容)と、
がん患者、その家族、そしてそれ以外で生きづらさを抱えている人に向き合い、そして著者自身がんになったことで気づいたこと、主に人間関係、とくに家族についての思いが書かれています。
衝撃を受けたのは、NASAの考える家族の定義、という部分です。
シャトルの打ち上げの際、
特別室で間近で見られるのは、見やすいからではなく、
大事故を起こした時に、いち早く手厚く心理的、医学的なサポートを行うためなのだそうです。
打ち上げの無事をみんなで見守るのですね。
そしてNASAのいう家族は
「血縁であること」ではないということ。特別室に親兄弟は含まれないのです。
血縁… 親は自分で選べない。
自分が選んだわけではない、ということです。
血縁だから…と、あきらめなくていい。
家族… 私も自分の身に置き換えてみる場面がたくさんありました。
安楽死についても書かれています。
安楽死には三種類あるということも初めて知りました。あまりにも無知。
日本ではまだまだ認めらそうにないだろうなと感じます。
延命措置を願うのは、患者ではなく家族「自分が悲しみたくない」という心理。
患者本人は耐え難い痛みから解放されたいと思っている…
医師は「あきらめたくない」と思っている。
あきらめたくない医師と
悲しみたくない家族が延命処置を施してしまい、命の限界まで闘病を強いられる…
どんな時も自分中心にしか考えられていないのなら人間だということ。
私だって限界を越えた苦しみなら、もう解放されたいと思うだろう。
芸能人ががんを公表し闘病ブログなど見ることがありますね。
あきらめない、闘う、それは本心だろう、と思います。
でも心の何処かに、大切な誰かを悲しませたくない、そんな思いも潜んでいるのかもしれない…この本を読んでからはそのように感じます。
自分の命は誰のものか。
安楽死はまさに、
死に方を選んでいるようで、
実は生き方を選んでいる…
死ぬということの正体は実は、
どう生きるか、ということ。
余命3年。って自分ならどうだろう。
3ヶ月なら整理すべきこともやるべきことも固まりそう。
でも3年って…
悲しむだけにしてはけっこう長いです。
生活もしていかなくちゃいけないし、
赤ちゃんだった子供は話ができるようになる年月…
この本からは
「すべて自分で選ぶ」を
強く受け止めました。
そんなこんなで、自分の時間をうまく買い取って、本をたくさん読みたいし、
手習いとして【読書感想文】しばらく書いてみようと思います。